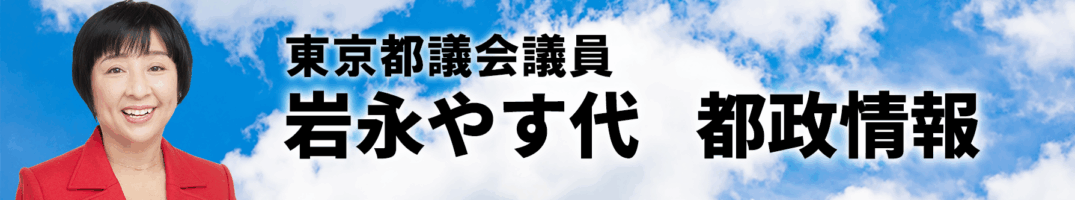2025年第2回定例会を終えて(談話)
2025年6月6日
都議会生活者ネットワーク 岩永 やす代
本日第2回定例会が閉会しました。
- 政治倫理条例について
都議会自民党の政治資金パーティーの裏金問題から政治倫理条例検討委員会が設置、条例の検討がされ、2本の条例案が上程されました。都議会生活者ネットワークは、共産党・立憲民主党・ミライ会議・自由を守る会・グリーンな東京とともに「東京都議会議員の政治資金に係る政治倫理の確立に関する条例」案の共同提案者となりましたが、否決され、都民ファースト・公明党・自民党提出の「東京都議会議員の政治倫理に関する条例」案が可決されました。この条例案には、現在最も問題になっている政治資金パーティーの自粛が入っておらず、反対しました。
いっぽう、この委員会発足の原因となった都議会自民党の裏金問題については、参考人として出席した2人の幹事長経験者への質疑でも全容解明には至っていません。本来、全容を明らかにし真相を究明したうえで、再発防止や政治倫理の確立に向けた議論を進めていくべきですが、この委員会ではできませんでした。告示が1週間後に迫った都議会議員選挙ですが、改選で問題が消えるわけではありません。来期においても全容解明や説明責任は必要です。
- 補正予算について
物価高騰で節約志向が広がるなか、猛暑が予想される夏の熱中症対策として、エアコン使用を控えることのないよう、水道の基本料金を無償とする補正予算が出されました。今年の夏の4か月に限る臨時特別措置で、1世帯当たり5000円程度の軽減、都内全域で368億円が計上されたものです。
都議選直前のこの時期に突然マスコミ発表されたこの措置には、多くの都民から「助かる」という声が届きました。物価高が続いているため、負担軽減が歓迎されるのは当然であり、賛成しました。しかし一方で、生活保護世帯や児童扶養手当を受給している世帯は、すでに基本料金が減免されているため対象にはならず、物価高騰が直撃し苦しい生活を強いられている世帯には届きません。困窮世帯にこそ支援が必要です。
全国的に水道需要が減り、過去に進めてきたダムなど多くの水源開発への負担金、水道施設の老朽化対策などで、他県では水道事業会計がひっ迫し、値上げせざるを得ないところが相次いでいます。東京都の水道料金は、全国の平均以下ですが、水道事業会計では、今後長きにわたる浄水場の更新や、水道施設の耐震・老朽化対策など、長期的な課題が多くあります。
そのような中で、一般会計からの繰り入れで実施する東京都の今回の措置は、他県からの「東京一人勝ち」論に拍車をかけ、さらなる軋轢を生むのではないかと懸念するところです。
- 学校を変えて学びの保障を
知事は、中学校の35人学級、都立高校の魅力向上や入試改革を表明しました。しかし、教育現場では教員不足が解消されず、休職・退職する教員も増えており、教員の働き方改革が言われていながらも改善されていません。私立高校の無償化により、公立高校離れがすすんでおり、都立高校の充実が求められています。また、不登校の子どもの数が右肩上がりに増えており、子どもが行きたくなると同時に、教員がのびのびと教育に取り組める学校へと変えていくことが急務です。
社会の縮図である学校が、インクルーシブな学びの場、障がいのあるなし、国籍や民族にかかわらず、子どもの頃からともに育ちあう場づくりを、子どもの声を聞きながらすすめていくことが大切です。「今」を生きる子どもたちの学びの保障が必要です。
少子化対策が言われて久しいですが、出生数はさらなる減少が続いています。今でも、家事、育児も介護も大きく女性にのしかかっています。選択的夫婦別姓制度さえできず、ジェンダー不平等を温存したまま、根強く残る家父長制的な現在の日本社会が、少子化の原因を女性に押しつけています。子どもを産もうと思える社会なのかが問われています。
待ったなしの気候危機対策をはじめとする環境問題、格差と分断が広がりますます重要になっている人権問題など、多様な人々が暮らす東京都には多くの課題があります。
都議会生活者ネットワークは、困難な時代にあっても、安心して生活できる持続可能なまち、環境・福祉優先の東京をつくるために、都議選での勝利をめざして全力で頑張っていきます。